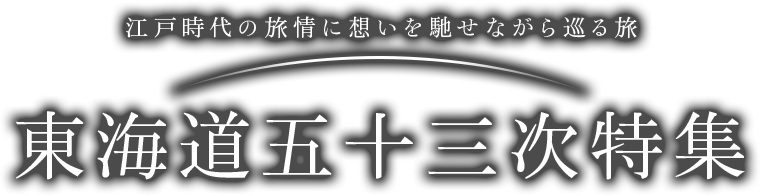
東海発
オリジナル
街道MAP
プレゼント!
全26回、総歩行距離約492kmを添乗員と行く、東海道五十三次街道を歩く旅。京都・三条大橋~東京・日本橋まで、53もの宿場を巡ります! おひとり様参加もお気軽にどうぞ。







宿場町と港町の機能を兼ね備え繁栄。

東海道と中山道の分岐点として繁栄。

伊勢路への街道として賑わった。

伊勢の参宮道、水口城の城下町として発展。

険しい鈴鹿峠の休泊場所として賑わった。

鈴鹿峠の麓にある。坂ノ下、阪之下とも。

江戸時代の交通の要。現在も街並を保存。

宿場町であると同時に城下町として発展。

安藤広重の傑作「庄野の白雨」として有名。

四日市宿⇔亀山宿間が長すぎたため設置。

海運・伊勢参宮街道として繁栄。

東海道唯一の海上路「七里の渡し」が有名。

熱田神宮の信仰の拠点として繁栄。

数多くの俳句を残した松尾芭蕉ゆかりの地。

馬市が立ったことで有名で浮世絵でも残る。

「二十七曲がり」と呼ばれる街道筋が特徴。

塩の道「吉良街道」に通じる交通の要所。

御油宿との宿場間は東海道で最も短い。

街道の面影を残す「御油の松並木」が有名。

江戸と近代の文化が混じり合う景観が特徴的

ほかの宿に比べるとかなり小規模の宿。

白須賀宿の柏餅は当時の名物だったとか。

地震や津波のため何度も移転。荒井宿とも。

「今切の渡し」があった宿。舞坂宿とも。

浜松城の城下町。最大規模の宿場町。

京から来て初めて富士山が見える場所。

江戸からも京からも27番目の宿場町。

掛川城の城下町として発展。

幕府直轄の宿場。歌川広重「日坂」で有名。

難所・小夜の中山峠を控えた宿。

東海道の難所の一つを控え賑わった宿。

田中城の城下町として発展。

夜具など別宿から借りる程、小規模な宿。

東海道中で最も小さい宿場。鞠子宿とも。

駿河国の政治の中心で東海道最大規模の宿場。

城下町や鍛治町などの職人の街として繁栄。

薩堙峠を越した休憩場所として賑わった宿。

小規模だが難所に備え賑わう。由井宿とも。

「富士川の川止め」で大いに賑わった宿。

流通の拠点にして富士参詣の宿。

水陸交通の拠点であり富士参詣の宿。

城下町で、漁業が盛んな宿。

伊豆半島の文化や産物の流通の中心。

五十三次の中で最も高い場所にあった宿。

箱根の山越えを控えた東海道屈しの大宿場。

尾上本陣の祖先が大名宿としたのが始まり。

小田原北条氏の城下町として発展。

多くの道が集まる、流通の中心地であった。

江戸出発で一泊目の宿泊地のため大盛況。

江戸側最初の難所の休泊場所として賑う。

県名・区名の由来になった宿。

品川宿⇔神奈川宿間が長すぎたため設置。

五街道の中でも重要視された東海道の初宿。